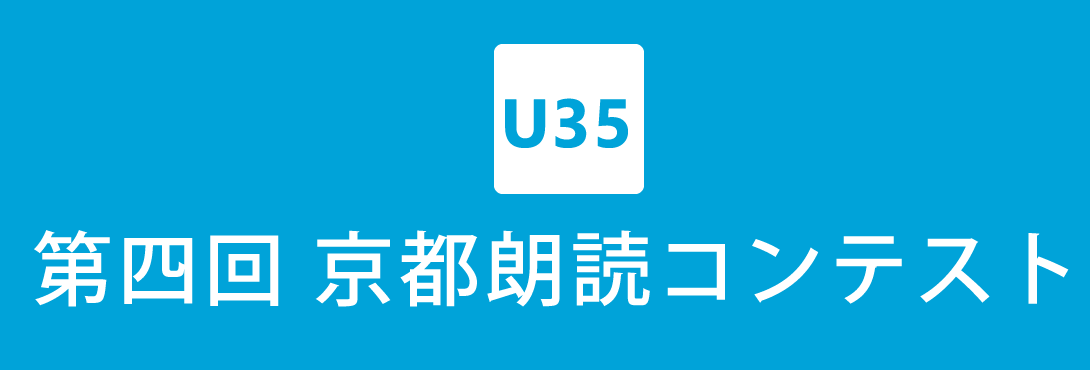
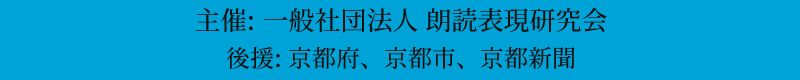
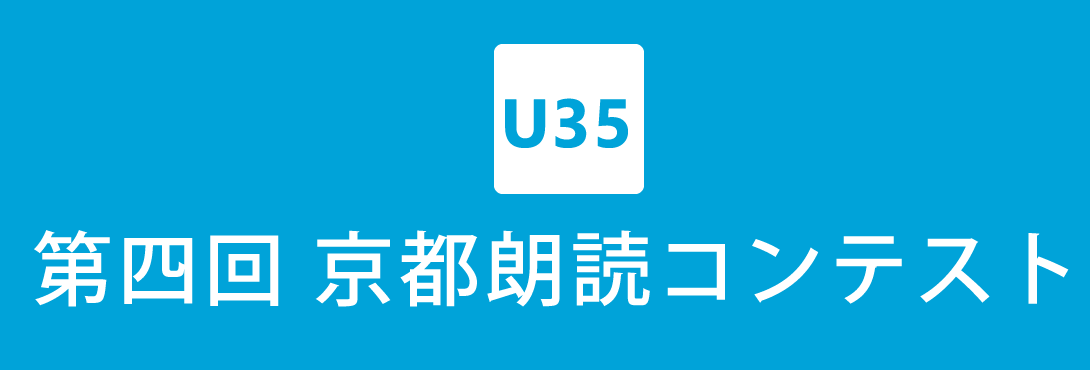
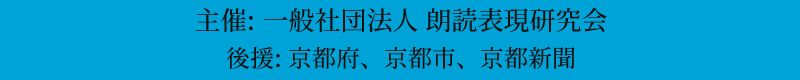
| 第四回を振り返ると、これまでの三回に比べて審査基準①にあたる“発声の基礎”を満たした声量のある朗読が増えたことが印象的でした。大変嬉しく思うと同時に、次のステップに進みつつあると感じます。 「①発声の基礎…声に力があるかどうか。舞台上での朗読を想定して、しっかりと声を届けることを意識してください。」(※公式サイト 審査基準より) 一方で、全体に声量はあるものの、コントロールが効かず発声の安定感に欠ける朗読も見られました。 ここからは、今回使用した4作品について触れておきます。 まず前回に続き、中村理聖さんから作品をご提供いただきました。 『ワンダーランド』については、冒頭の「いつか海外へ行く」という友人のセリフまでを大きな表現で読んでしまい、その後の「それが彼の口癖で」へ自然に繋がらないケースが目立ちました。また、登場するウサギのキャラクターに色をつけること自体は魅力的ですが、そのセリフだけが浮き立ち、結果として物語全体のトーンを損なうこともありました。 最もバランスの取れた朗読が多かったのは『観覧車』でした。前半はセリフがなく地の文中心であるため、朗読者が世界観を作りやすく、結果的に安定感のある表現に繋がったのかもしれません。 最後に『朝の走者』。以前にも使用した作品ですが、冒頭から「僕」の視点で進むため、すべてをセリフのように朗読することも可能です。その意味で、地の文の朗読が苦手な人にとっては取り組みやすい作品だったでしょう。ただし、朗読としてどこまでセリフに寄せるかは各自の判断に委ねられるため、力量が問われる部分でもありました。 今後も皆さんがそれぞれの課題に取り組みながら、さらに豊かな朗読を届けてくれることを期待しています。 |
| 一般社団法人 朗読表現研究会 代表理事 佐野真希子 |